あなたは「人手不足で採用活動をしても若者の応募が来ない」「若者はどこに行ってしまったのか」と思ったことはありませんか?結論、若者は大企業やフリーランス、新しい働き方を選択しています。この記事を読むことで人手不足の真の原因と効果的な解決策がわかるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。
Contents
1.人手不足で若者はどこへ消えた?現状と背景を解説

人手不足の深刻化:企業の52.6%が人材確保に苦戦
2024年12月時点で、日本企業の52.6%が人手不足を感じており、これは過去最高水準となっています。
特に深刻なのは正社員の確保で、企業の約半数が必要な人材を集められない状況に陥っています。
人手不足による倒産件数も急増しており、2024年には342件と前年比約1.3倍に達し、過去最多を記録しました。
この背景には、少子高齢化による構造的な問題だけでなく、企業間での人材争奪戦の激化があります。
採用活動を強化しても応募者が集まらず、たとえ採用できても短期間で退職してしまうケースが多発しています。
少子高齢化による若年労働人口の減少実態
日本の15歳から24歳の人口は、1990年代初頭の1,800万人以上から2023年には約1,132万人まで大幅に減少しています。
生産年齢人口(15~64歳)も1995年の約8,716万人をピークに減少を続け、2023年には7,400万人を下回りました。
2040年には労働力人口がさらに1,100万人減少すると予測されており、人手不足は今後ますます深刻化する見込みです。
特に地方では若年層の都市部への流出と相まって、働き手の絶対数が不足している状況が続いています。
この人口減少は一時的な現象ではなく、構造的な問題として長期間にわたって企業経営に影響を与え続けるでしょう。
若者が大企業に集中する求人倍率格差の実情
2024年3月卒の就職活動において、従業員5000人以上の大企業の求人倍率は約0.4倍と買い手市場になっています。
一方、従業員300人未満の中小企業では求人倍率が約6.2倍と完全な売り手市場となっており、大きな格差が生まれています。
若者が大企業を選ぶ理由として、安定した給与や充実した福利厚生、明確なキャリアパスなどが挙げられます。
さらに大企業では研修制度やスキルアップの機会が豊富で、若者が重視する成長環境が整っているケースが多いのです。
中小企業にとって、限られた若年層の人材を大企業と競って確保することは極めて困難な状況となっています。
地方から都市部への若者流出による地域格差
2023年の東京23区への転入者数は約40万人で、そのうち20代が約50%を占めています。
地方の若者が都市部に移住する理由は、仕事の選択肢の多さ、高い賃金水準、充実した生活インフラなどがあります。
特に大学進学や就職を機に都市部に移住した若者は、そのまま定住するケースが多く、地方への還流が少ないのが現状です。
都市部には大企業の本社や支社が集中しており、キャリアアップの機会やスキル向上の場が豊富に存在します。
この人口流出により、地方の企業は若手人材の確保がますます困難になり、人手不足が深刻化する悪循環に陥っています。
2.若者の価値観変化が人手不足に与える影響

ワークライフバランス重視で変わる仕事選びの基準
現代の若者は仕事選びにおいて、給与や安定性だけでなく、仕事とプライベートの調和を重視するようになっています。
長時間労働や休日出勤が当たり前の職場環境は敬遠され、柔軟な働き方ができる企業に人気が集まっています。
年間休日数や有給休暇の取得率、残業時間の実態などが企業選びの重要な判断材料となっています。
Z世代の退職理由として最も多いのは「人間関係の悪さ」で46%を占めており、良好な職場環境への関心の高さがうかがえます。
企業は若者のワークライフバランス重視の傾向を理解し、働きやすい環境づくりに積極的に取り組む必要があります。
成長機会と働きやすさを両立する職場を求める傾向
若者は単に働きやすい職場を求めるだけでなく、自身のスキルアップやキャリア形成ができる成長機会も重視しています。
知識やスキルの獲得に関する項目への関心は年々上昇しており、学習意欲の高い若者が増えています。
「ここで成長できるか」という視点で職場を評価し、将来のキャリアビジョンに合致する企業を選ぶ傾向が強まっています。
研修制度やメンター制度、社外学習の支援など、人材育成に力を入れている企業が若者から選ばれやすくなっています。
企業は働きやすさと成長機会の両方を提供することで、優秀な若手人材の獲得と定着を実現できるでしょう。
転職への抵抗感薄れとキャリアアップ志向の高まり
終身雇用制度への依存が薄れ、転職を通じたキャリアアップを前向きに捉える若者が増加しています。
現代の若者は一つの会社で長期間働くことよりも、複数の企業での経験を積むことでスキルを磨こうと考えています。
新規大卒者の32.3%が3年以内に離職している現状は、若者の転職に対する価値観の変化を如実に表しています。
企業間での人材流動性が高まることで、優秀な人材の確保と維持がより困難になっています。
企業は若者の転職志向を受け入れつつ、魅力的なキャリアパスを提示して人材の定着を図る戦略が求められています。
フリーランス・リモートワークなど新しい働き方への注目
インターネットの普及により、フリーランスやリモートワークなど場所に縛られない働き方が広がっています。
自分のペースで仕事を進められ、ワークライフバランスを重視する若者にとって、これらの働き方は魅力的な選択肢となっています。
スキルアップやキャリアチェンジの機会も多く、自己成長を求める若者に支持されています。
人材派遣会社には毎月80人程度の若者が中途採用で入社しており、従来の働き方にとらわれない若者が増えています。
企業は正社員としての雇用だけでなく、業務委託やプロジェクトベースでの人材活用も検討する必要があります。
3.業界別に見る人手不足の現状と若者が避ける職種
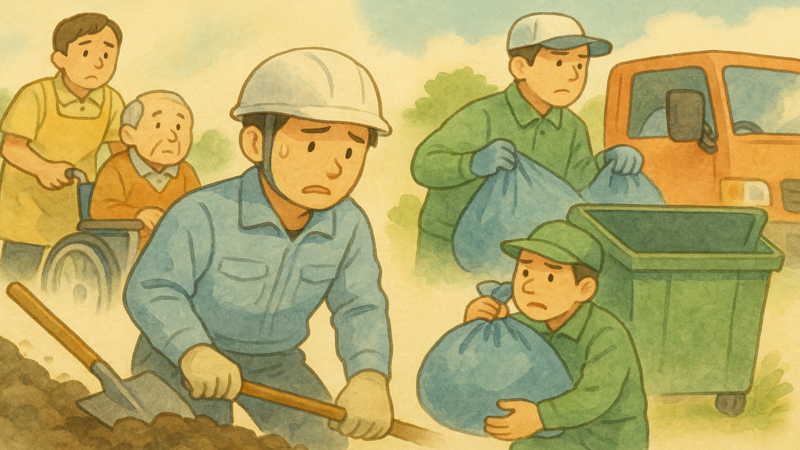
最も人手不足が深刻な業界ランキングトップ5
2024年の調査において、正社員の人手不足が最も深刻な業界は以下の通りです:
- 1位:情報・サービス業(70.2%)
- 2位:メンテナンス・警備・検査業(69.7%)
- 3位:建設業(69.6%)
- 4位:金融業(67.1%)
- 5位:運輸・倉庫業(65.8%)
情報サービス業は企業のDX推進需要の高まりにより、IT人材の確保が急務となっています。
建設業や運輸業では2024年問題による労働時間規制の影響で、人手不足がさらに深刻化しています。
これらの業界では求人を出しても応募者が集まらず、事業拡大や新規プロジェクトの実施に支障をきたしているケースが多発しています。
若者に敬遠される3K(きつい・汚い・危険)職種の実態
建設業、介護業、製造業など、いわゆる3K職種は若者から敬遠されがちな傾向があります。
これらの職種は「体力的にきつい」「給与が低い」「キャリアアップが見えにくい」「プライベートの時間を確保しにくい」などの理由で不人気です。
介護職や建設業の求人倍率は他の業種に比べて非常に高く、求人数に対して応募者が大幅に不足している状況が続いています。
若者が重視するワークライフバランスや成長機会の提供が困難な職場環境が、人材確保の障壁となっています。
これらの業界では労働環境の改善、給与水準の引き上げ、キャリアパスの明確化などの根本的な改革が急務となっています。
IT・情報サービス業界での人材争奪戦の激化
約8割の企業がDXを担うIT人材の量と質が「大幅に不足している」または「やや不足している」と回答しています。
特に不足しているのは、従来型のIT人材ではなく、AI、IoT、データ分析などの最先端技術を扱える人材です。
IT業界では高いスキルを持つ人材が好条件で大手企業に採用されやすく、中小企業の人材確保は極めて困難な状況です。
エンジニアの年収相場も上昇傾向にあり、人材確保のためのコストが急激に増加しています。
企業はIT人材の育成投資や外部パートナーとの協業など、多角的なアプローチが必要となっています。
介護・建設・運輸業界で顕著な人手不足問題
介護業界では高齢化の進展により需要が急増する一方で、労働条件の厳しさから人材確保が困難な状況が続いています。
建設業界では技能労働者の高齢化と若手の入職者不足により、技術継承が大きな課題となっています。
運輸業界では宅配需要の増加と2024年問題による労働時間規制により、ドライバー不足が深刻化しています。
| 業界 | 主な課題 | 人手不足率 |
|---|---|---|
| 介護 | 低賃金、夜勤負担 | 3.2% |
| 建設 | 3K職場、技術継承 | 69.6% |
| 運輸 | 長時間労働、高齢化 | 65.8% |
これらの業界では国や業界団体による支援策も講じられていますが、根本的な解決には時間がかかると予想されます。
4.企業が若者に選ばれるための具体的対策と成功事例

働き方改革と労働環境改善による人材確保戦略
企業は若者に魅力的な職場として選ばれるために、働き方改革を積極的に推進する必要があります。
フレックスタイム制度やテレワークの導入により、柔軟な働き方を実現している企業に若者の注目が集まっています。
年間休日数の増加、有給休暇取得率の向上、残業時間の削減などの具体的な成果を示すことが重要です。
社内コミュニケーションの改善や風通しの良い職場環境づくりも、若者の職場選びに大きく影響します。
定期的な従業員満足度調査を実施し、働きやすさの改善に継続的に取り組む姿勢を示すことで、人材の定着率向上が期待できます。
給与・待遇の見直しと福利厚生の充実化
人手不足を背景として、企業の76.6%が「労働力の定着・確保」を理由に賃上げを実施しています。
給与水準の見直しだけでなく、住宅手当、交通費支給、食事補助などの福利厚生の充実も重要な要素です。
特に若者が重視する項目として、スキルアップ支援、資格取得支援、語学研修などの自己成長に関する福利厚生があります。
副業許可制度や社内起業制度など、多様なキャリア形成を支援する制度も若者の関心を集めています。
中小企業でも創意工夫により、大企業に負けない魅力的な待遇パッケージを構築することが可能です。
業務効率化・DX推進で解決する人手不足対策
人手不足の根本的な解決策として、業務効率化による生産性向上が注目されています。
RPAやAIツールの導入により、定型業務の自動化を進めることで、限られた人材でより多くの業務をこなせるようになります。
ペーパーレス化やクラウドシステムの活用により、業務プロセスの簡素化と効率化を実現できます。
社員のマルチタスク化を進めることで、部署をまたいだ柔軟な人材配置が可能になります。
DX推進により、若者が好む最新技術を活用した職場環境を提供することで、人材の魅力向上にもつながります。
外国人材活用とアウトソーシングによる解決策
外国人労働者の雇用は人手不足解消の有効な手段として、多くの企業で活用が進んでいます。
特定技能制度の拡充により、より多くの分野で外国人材の受け入れが可能になっています。
外国人材は高いモチベーションを持ち、異文化の視点を組織にもたらすメリットもあります。
アウトソーシングの活用により、ノンコア業務を外部に委託し、社内のコア人材を重要業務に集中させることができます。
人材派遣や業務委託を効果的に組み合わせることで、必要な時に必要な人材を確保する柔軟な体制を構築できます。
成功企業に学ぶ若者採用・定着の実践事例
山梨県のある旅館では、部署統合によるマルチタスク化を進め、中抜け勤務を削減し年間休日数を増加させました。
この取り組みにより人手不足をカバーできただけでなく、労働環境の改善により求人への応募者が増加しました。
沖縄県の建設会社では、受注基準を見直して高収益・工期に余裕のある案件を選別することで、従業員負担を軽減しました。
船橋株式会社では採用ページの改善により女性の採用数を増加させ、多様な人材の活用を実現しました。
これらの成功事例に共通するのは、従業員の働きやすさを追求し、持続可能な成長を目指している点です。
成功企業では経営トップが人材確保の重要性を認識し、全社を挙げて労働環境の改善に取り組んでいます。
まとめ
この記事を通じて、人手不足で若者がどこへ向かっているかと、企業が取るべき対策についてお伝えしました。重要なポイントをまとめると以下の通りです:
- 企業の52.6%が人手不足を実感し、若年労働人口は1990年代から大幅に減少している
- 大企業と中小企業の求人倍率格差が拡大し、若者の多くが大企業に集中している
- 地方から都市部への若者流出により、地域格差が深刻化している
- 若者の価値観はワークライフバランスと成長機会の両立を重視する方向に変化している
- フリーランスやリモートワークなど新しい働き方への関心が高まっている
- 3K職種や労働環境の厳しい業界では特に人手不足が深刻化している
- IT・情報サービス業界では最先端技術人材の争奪戦が激化している
- 働き方改革と労働環境改善が人材確保の重要な戦略となっている
- 給与・待遇の見直しと福利厚生の充実が競争力向上に直結している
- DX推進や外国人材活用など多角的なアプローチが解決策として有効である
人手不足は一朝一夕に解決できる問題ではありませんが、若者の価値観を理解し、魅力的な職場環境を構築することで必ず改善できます。今こそ企業が変革に取り組み、持続可能な成長を実現する絶好の機会です。ぜひ本記事で紹介した対策を参考に、あなたの会社でも人材確保の成功を掴んでください。


