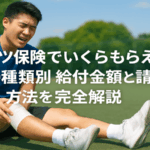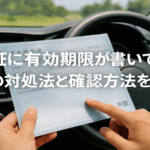あなたは松任谷由実の「リフレインが叫んでる」というタイトルの意味について疑問に思ったことはありませんか?結論、この楽曲は繰り返される記憶や感情の叫びを表現した深い恋愛ソングです。この記事を読むことで楽曲タイトルの真の意味と歌詞に込められたメッセージがわかるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。
Contents
1.「リフレインが叫んでる」楽曲の基本情報とその意味

松任谷由実による1988年の名曲の背景
「リフレインが叫んでる」は、1988年11月26日に発売された松任谷由実の20枚目のオリジナルアルバム『Delight Slight Light KISS』に収録された楽曲です。
この楽曲が生まれた背景には、ユーミン自身の音楽的な成熟と、1980年代後半の日本の社会情勢が大きく影響しています。
バブル経済の絶頂期に作られたこの楽曲は、表面的な華やかさとは対照的に、人間の内面にある深い感情を描写しています。
ユーミンは当時、恋愛や人生の複雑さを音楽で表現することに強いこだわりを持っており、この楽曲もその思想が色濃く反映された作品となっています。
楽曲制作時のエピソードとして、湘南海岸でのドライブ中に聞いた古いカセットテープからインスピレーションを得たという話も残されており、リアルな体験に基づいた楽曲であることがうかがえます。
三菱自動車CMソングとしての起用とヒットの理由
この楽曲は三菱自動車の「新型ミラージュ」のCMソングとして起用され、シングルカットされていないにも関わらず大きな話題となりました。
CMでの使用により、ユーミンファン以外にも楽曲の認知度が急速に広がりました。
特に印象的なイントロ部分が多くの人の記憶に残り、有線チャートでは見事に1位を獲得するという快挙を成し遂げています。
CMソングとしての成功の要因は、楽曲の持つ都市的でありながら切ない雰囲気が、車での移動というシチュエーションと完璧にマッチしたことにあります。
また、1989年には日本レコード大賞で優秀アルバム賞を受賞するなど、音楽業界からも高い評価を受けました。
この楽曲の成功は、後のユーミンの楽曲制作にも大きな影響を与え、商業的成功と芸術性を両立させる一つのモデルケースとなりました。
「リフレインが叫んでる」というタイトルの意味とは
楽曲タイトルの「リフレインが叫んでる」とは、文字通り「繰り返される部分が叫んでいる」という意味を持ちます。
ここでいう「リフレイン」は音楽用語としての意味と、心の中で繰り返される記憶や感情という二重の意味を持っています。
楽曲の中では、古いカセットテープから流れる音楽のリフレイン部分が、まるで過去の恋愛の記憶を蘇らせるように「叫んでいる」という状況が描かれています。
この表現は、音楽が持つ強力な記憶喚起の力を詩的に表現したものであり、多くの人が経験する「音楽によって過去の感情が蘇る」という現象を見事に言語化しています。
また、「叫んでる」という動詞の使用により、単なる繰り返しではなく、感情的で切迫した状況であることが強調されています。
このタイトルは、楽曲全体のテーマである「記憶の中で永遠に繰り返される恋の痛み」を端的に表現した秀逸なネーミングといえるでしょう。
アルバム『Delight Slight Light KISS』での位置づけ
『Delight Slight Light KISS』は、ユーミンの音楽キャリアの中でも特に重要な位置を占めるアルバムです。
このアルバムは、ユーミンの楽曲制作における一つの転換点となった作品で、より洗練された音楽性と深い歌詞表現が特徴となっています。
「リフレインが叫んでる」は、このアルバムの中でも特に印象的な楽曲として位置づけられており、アルバム全体のコンセプトを象徴する重要な役割を果たしています。
アルバムタイトルの「Delight Slight Light KISS」が示すように、微細な光と軽やかなキスという繊細な表現が全体を貫いており、「リフレインが叫んでる」もその世界観の中で重要な意味を持っています。
楽曲の配置や他の収録曲との関係性も計算されており、アルバムを通して聞くことで、より深い感動を得られる構成となっています。
このアルバムでの成功により、ユーミンは単なるポップスシンガーから、日本の音楽シーンにおける重要なアーティストとしての地位を確立しました。
2.楽曲の歌詞に込められた深いメッセージ解釈

「どうして出逢ってしまったのだろう」という後悔の表現
楽曲の冒頭で歌われる「どうして どうして僕たちは 出逢ってしまったのだろう」という歌詞は、恋愛の終わりに感じる深い後悔を表現しています。
この表現は、一般的な失恋ソングとは異なり、出会いそのものを否定するという強烈なメッセージを含んでいます。
通常、恋愛が終わった時には「別れたくない」「戻りたい」という感情が歌われることが多いのですが、この楽曲では出会いから否定するという、より根本的で深刻な後悔が描かれています。
「出逢ってしまった」という表現の「しまった」には、取り返しのつかない失敗をしたという強い後悔の念が込められています。
この歌詞は、愛していたからこそ別れが辛く、いっそ出会わなかった方が良かったという、愛の深さの裏返しとしての絶望を表現しています。
現代においても多くの人が共感できる普遍的な感情であり、恋愛経験者なら誰もが一度は感じたことのある複雑な心境を見事に言語化した名詞といえるでしょう。
別れた恋人への想いと湘南海岸の舞台設定
楽曲の舞台は湘南海岸、特に葉山から秋谷海岸にかけての地域が設定されており、実際の地名が歌詞に織り込まれています。
海岸沿いのドライブデートという設定は、1980年代の恋愛文化を象徴的に表現しており、多くのリスナーが共感できるシチュエーションとなっています。
「最後の春に見た夕陽は うろこ雲照らしながら ボンネットに消えてった」という歌詞からは、二人が最後に過ごした美しい瞬間が鮮明に描写されています。
湘南海岸という開放的で美しい場所が舞台となることで、恋愛の終わりの悲しさがより一層際立って表現されています。
楽曲の中では、主人公が一人でその場所を再び訪れ、過去の記憶と向き合うという構造になっており、場所と記憶の結びつきの強さが表現されています。
このような具体的な地域設定により、楽曲に現実感とリアリティが生まれ、聞く人の心により深く響く作品となっています。
「すりきれたカセット」が叫ぶリフレインの悲しさ
「すりきれたカセットを 久しぶりにかけてみる 昔気づかなかった リフレインが悲しげに叫んでる」という歌詞は、楽曲の核心部分です。
カセットテープという1980年代を象徴するアイテムの使用により、時代性と共に懐かしさが演出されています。
「すりきれた」という表現は、何度も繰り返し聞いたことを示しており、その音楽が二人にとって特別な意味を持っていたことがわかります。
「昔気づかなかった」という部分は、恋愛中には見えていなかった音楽の持つ深い意味が、別れた後になって初めて理解できるようになったことを示しています。
恋愛中は幸せで聞いていた音楽が、別れた後には悲しい記憶を呼び起こすものに変わってしまうという、音楽と感情の複雑な関係が巧妙に表現されています。
この部分は、楽曲タイトルの「リフレインが叫んでる」の具体的な状況を説明する重要な歌詞であり、多くの人が経験する「音楽による記憶の蘇生」を詩的に描写した名詞です。
記憶の中で繰り返される恋の痛みと切なさ
楽曲全体を通して、主人公の心の中で恋愛の記憶が何度も繰り返されている状況が描かれています。
「ひき返してみるわ ひとつ前のカーブまで いつか海に降りた あの駐車場にあなたがいたようで」という歌詞からは、物理的に過去の場所を訪れることで記憶を辿ろうとする主人公の姿が見えます。
記憶の中の恋人はもはや現実には存在しないにも関わらず、その場所に行けば会えるような錯覚を抱いてしまう心理状態が繊細に表現されています。
この楽曲では、時間の経過と共に痛みが和らぐという一般的な失恋の描写ではなく、記憶が永続的に繰り返されることの苦しさが中心テーマとなっています。
「人は忘れられぬ景色を いくどかさまよううちに 後悔しなくなれるの」という歌詞は、時間が経てば後悔も薄れるという希望を示しながらも、疑問形で終わることで不確実性を表現しています。
この構造により、楽曲は単なる失恋ソングを超えて、人間の記憶と感情の複雑さを探求した深い作品となっています。
3.リフレインという言葉の本来の意味と音楽での役割

音楽用語としてのリフレインの定義と使われ方
リフレインとは、音楽用語として「楽曲や歌詞の一節の最後を何度も繰り返すこと」を意味します。
日本語では「反復句」「繰り返し句」「畳句」とも呼ばれ、フランス語読みでは「ルフラン」と表現されることもあります。
有節形式の楽曲において、各節の後に繰り返される同一の歌詞やメロディーを指し、聞く人の記憶に残りやすくする効果があります。
リフレインは楽曲の主題や印象的なフレーズを強調する役割を果たし、楽曲全体にまとまりと統一感をもたらします。
クラシック音楽から現代のポップスまで、あらゆるジャンルの音楽で使用される基本的な構成要素の一つです。
特に民謡や賛美歌などでは、ソロ部分とリフレイン部分を分けて歌うことが多く、聴衆参加型の音楽では重要な役割を果たしています。
現代の楽曲制作においても、キャッチーなリフレインの存在が楽曲の商業的成功に大きく影響することが知られています。
英語「refrain」の語源と二つの意味(控える・繰り返し)
英語の「refrain」には、動詞として「控える・差し控える」という意味と、名詞として「繰り返し・反復句」という意味の二つがあります。
語源はラテン語の「refraindre」(抑制する)と古フランス語の「refraindre」に由来しており、元々は「抑制する」という意味を持っていました。
動詞としての使用例では「Please refrain from smoking」(喫煙をお控えください)のように、何かの行為を一時的に控えるように丁寧にお願いする際に使われます。
名詞としての「refrain」は、フランス語の「refrain」(繰り返す)が語源となっており、音楽や詩における反復部分を指します。
この二つの意味は一見関連性がないように見えますが、どちらも「一定の行為や状態を保持する」という共通点があります。
日本でカタカナ語として使われる「リフレイン」は、主に名詞としての意味(繰り返し)で使用されることがほとんどです。
ユーミンの楽曲タイトルでは、この「繰り返し」の意味でリフレインという言葉が使用されており、音楽的な繰り返しと感情的な繰り返しの双方を表現しています。
リピートやルフランとの違いと使い分け
リフレインと類似の言葉として「リピート」や「ルフラン」がありますが、それぞれ微妙に異なる意味を持っています。
リピートは「楽曲を繰り返すこと」全般を指し、繰り返す部分が楽曲のどの部分でも構いませんが、リフレインは主に各節の最後に来る繰り返し部分に限定されます。
ルフランはフランス語読みのリフレインのことで、基本的に同じ意味ですが、クラシック音楽や芸術音楽の分野でよく使用される傾向があります。
音楽理論的には、リフレインは楽曲構成における特定の位置と機能を持つ要素として定義されています。
一般的な使い分けとしては以下のようになります:
- リフレイン: 各節の最後の反復句
- リピート: 楽曲全体の繰り返し
- ルフラン: クラシック音楽でのリフレイン
日常会話では「リフレイン」が最も広く使われており、楽曲の繰り返し部分全般を指す場合も多くあります。
楽曲構成におけるリフレインの効果と重要性
リフレインは楽曲の構成において、聞き手の記憶に残りやすくする重要な機能を果たしています。
心理学的な観点から見ると、繰り返しによって情報が長期記憶に定着しやすくなるという「反復効果」があり、リフレインはこの原理を音楽に応用したものです。
楽曲の感情的なメッセージを強調し、聞き手の心に深く印象を残す効果があります。
商業音楽においては、リフレインの存在が楽曲の「フック」(聞き手を引きつける要素)として機能し、ヒット曲の条件の一つとされています。
また、ライブパフォーマンスにおいては、観客が一緒に歌える部分として機能し、アーティストと観客の一体感を生み出す重要な役割を果たします。
楽曲の構造的な面では、リフレインがあることで楽曲全体にまとまりが生まれ、散漫になりがちな長い楽曲でも統一感を保つことができます。
「リフレインが叫んでる」という楽曲では、この音楽理論的なリフレインの概念を歌詞の中に取り込むことで、メタ的な表現を実現した革新的な作品となっています。
4.「リフレインが叫んでる」が現代に与える影響と魅力

数々のアーティストによるカバーバージョンの意義
「リフレインが叫んでる」は発表から30年以上経った現在でも、多くのアーティストによってカバーされ続けている楽曲です。
カバーアーティストには以下のような多様な顔ぶれが含まれています:
- A.S.A.P. (1991年) – アルバム『Refrain』に収録
- 西城秀樹 (1998年) – シングル「2Rから始めよう」c/wに収録
- 河村隆一 (2012年) – アルバム『The Voice 2』に収録
- Aimer – 現代的なアレンジでの楽曲解釈
これらのカバーバージョンが生まれる理由は、楽曲の持つ普遍的なテーマと、時代を超えて共感できるメッセージにあります。
各アーティストが自分なりの解釈を加えることで、楽曲に新たな生命が吹き込まれ、異なる世代のリスナーに届けられています。
カバーされることで原曲の価値も再評価され、ユーミンの楽曲の奥深さと完成度の高さが改めて証明されています。
現代のアーティストたちがこの楽曲を選んでカバーするということは、楽曲が持つメッセージが現在でも色褪せていない証拠といえるでしょう。
ドラマ主題歌としての使用と世代を超えた愛され方
「リフレインが叫んでる」は数多くのテレビドラマの主題歌として使用され、映像作品との相性の良さを証明しています。
主要な使用作品には以下があります:
- TBS系ドラマ23『東京ホテル物語』主題歌 (1989年)
- TBS『ルージュの伝言』 (1991年、第8話/主演・富田靖子)
- TBS系『ユーミン・ドラマブックス』 (1991年、出演:有森也実、東幹久、渡辺満里奈)
- NHK『Yuming Films』 (2007年12月29日、第1話/監督:窪田崇、主演:本仮屋ユイカ)
これらのドラマでの使用により、楽曲は音楽ファン以外の幅広い層にも親しまれるようになりました。
特に恋愛ドラマでの使用が多いのは、楽曲の持つ深い恋愛感情の表現が、映像作品の感情的な場面と完璧にマッチするためです。
世代を超えて愛される理由として、楽曲のテーマが人間の普遍的な感情を扱っているため、時代が変わっても色褪せない魅力を持っていることが挙げられます。
現在でも再放送や配信サービスでこれらの作品が視聴される際、新たなリスナーがこの楽曲と出会う機会が生まれ続けています。
現代の恋愛観と共鳴する普遍的なテーマ性
「リフレインが叫んでる」が描く恋愛の複雑さと痛みは、現代の恋愛観とも深く共鳴する普遍的なテーマを持っています。
現代社会においても、SNSや音楽ストリーミングサービスを通じて過去の恋愛を思い出すきっかけが増えており、楽曲が描く「音楽による記憶の蘇生」はより身近な体験となっています。
デジタル時代の現在では、カセットテープの代わりにプレイリストや楽曲履歴が過去の記憶を呼び起こすツールとなっており、楽曲のメッセージの本質は変わっていません。
現代の恋愛においても、別れの痛みや後悔の念は変わらず存在し、時には「出会わなければ良かった」と思うほどの深い傷を残すことがあります。
また、現代人の多くが経験する「音楽によって過去の感情が蘇る」という現象は、楽曲が35年前に予見していたテーマでもあります。
インターネットやSNSにより過去の恋人との接点が完全に断たれることが少なくなった現代において、記憶との向き合い方はより複雑になっており、楽曲のメッセージはむしろ現代により適している側面もあります。
この普遍性こそが、楽曲が長年にわたって愛され続け、現代の若いリスナーにも深く響く理由といえるでしょう。
まとめ
この記事を通じて「リフレインが叫んでる」の意味と魅力について詳しく解説してきました。記事全体から読み取れる重要なポイントをまとめます:
- 「リフレインが叫んでる」は1988年発表のユーミンの代表作で、音楽の繰り返し部分が過去の記憶を呼び起こす状況を描いた楽曲
- 楽曲タイトルは「繰り返される部分が叫んでいる」という意味で、音楽と記憶の深い関係を表現している
- 「どうして出逢ってしまったのだろう」という歌詞は、愛の深さゆえの後悔を表現した印象的なフレーズ
- 湘南海岸を舞台とした具体的な地域設定により、リアリティと共感性を高めている
- リフレインという音楽用語には「繰り返し」と「控える」という二つの意味がある
- 三菱自動車のCMソングとして大ヒットし、有線チャート1位を獲得した
- 多くのアーティストにカバーされ、数々のドラマ主題歌として使用されている
- 現代の恋愛観とも共鳴する普遍的なテーマを持ち、世代を超えて愛され続けている
「リフレインが叫んでる」は単なる恋愛ソングを超えて、人間の記憶と感情の複雑さを探求した深い芸術作品です。現代を生きる私たちにとっても、音楽と記憶の関係について考えさせてくれる貴重な楽曲といえるでしょう。あなたも改めてこの名曲を聞き直してみて、その深いメッセージを感じ取ってみてください。
関連サイト
- 日本音楽著作権協会(JASRAC) – https://www.jasrac.or.jp/
- 松任谷由実公式サイト – https://yuming.co.jp/